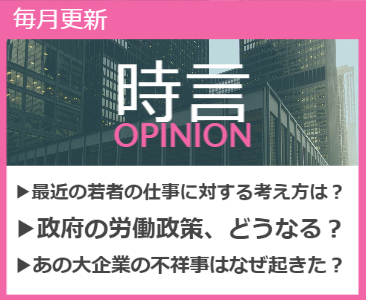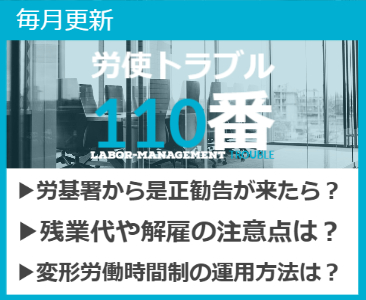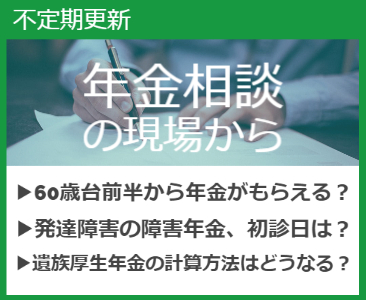労使トラブル110番
最高裁マタハラ判決を正確に理解する
Q
妊娠・出産(産休)その後の育児休業を予定している女性職員(課長職)からの申請に基づき、休業(それに伴う課長職の停止)させていたのですが、育児休業終了に伴い復職させるとき主任職(課長の1ランク下位の職)としました(その職場には課長職は1人のみで、他の管理職は主任のみという事情がある)。たしかに「課長→主任」に伴いその分給与が若干減額となります。やむを得ない措置と考えていたのですが、その職員から「不利益変更ではないか」という訴えがありました。どう考えればいいのでしょうか。
A
【給与減が伴えば不利益変更となる】
確かに職場の事情から「課長→主任」に変更せざるを得ないというのがあるとしても、そのことによって給与が減額となってしまえば不利益変更と言わざるを得ないでしょう。まして、労働者本人が納得していないようですので、このまま強行すると裁判も想定されますので、強行すべきではありません。
【最高裁2014年10月23日マタハラ判決とは】
最高裁は2014年10月23日、妊娠を理由にした降格は、男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法と判断しました。
この事件は、広島市の病院で理学療法士として勤めていた女性が、妊娠したために負担の軽い業務を希望したところ、新たな業務に就く際に副主任という役職を降ろされ(月5,000円の副主任手当を失った)、育児休業明けの復職時にも副主任に復帰できないままとなったことから、慰謝料などを求めたものです。何が問われ、今後の判断をする際の基準はどう変わったのかが大事な点です。
(1)均等法9条3項、育児介護休業10条は強行規定
均等法9条3項とは、「事業主、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」。育児・介護休業法10条とは、「労働者が育児休業申出をし、又は育児休業したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」。この2つの規定は強行規定(=規定に反する法律行為は無効であるとする規定)であるとしています。
(2)本人の「同意」があったのか
判決では、上記強行規定違反に問われない場合、例外として認め得る場合とは、①労働者との真なる合意があった場合と、②業務上やむを得ない「特段の事情」があった場合のみとしています。今回の措置に関して労働者は不満を述べていますから、「真なる合意」があったとはいえません。
最高裁判決後、法律等の改定も行われ、下級審の判断も大きく変わりました。
【給与減額を避ける措置を検討する】
もしご相談の職場では、課長職が1つしかない、他はすべての管理職の職位は主任のみであるとするならば、検討する必要があるのは、課長職でもらっていた給与からの減額をいかに避けるかということにならざるを得ないでしょう。激変緩和措置も含めてご検討ください。