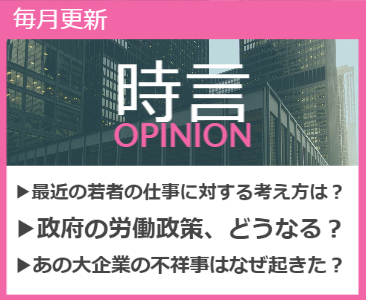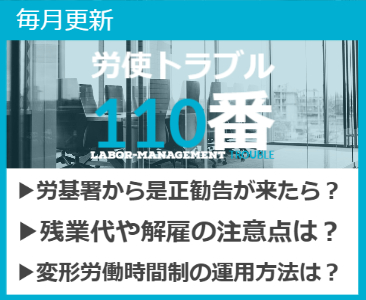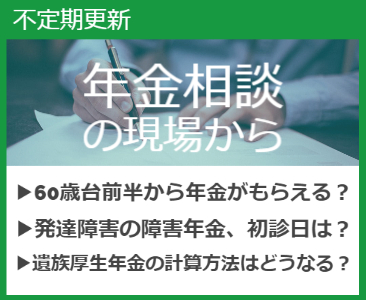労使トラブル110番
雇用終了時に問題となる「有期雇用契約か、無期雇用契約か」
Q
清掃業務を会社から請け負っています。単年度ごとの競争入札方式で、単年度ごとに業務を受注できるどうかが決まります。今年度受注できる予定だった会社さんから、「今年度は他社に依頼するので御社は受注できません」と突然連絡がありました。その会社を請け負うために従業員を雇用しているのですが、突然の連絡で、辞めさせなければならないのですが、雇用契約は「無期雇用」としていたため、解雇となります。争いになる場合もあると思いますが…。
A
【有期雇用とする根拠とは】
安易に有期雇用とする例が多いのは確かです。「非常勤だから」という理由で1年単位の有期雇用とする例が多いのは確かで、「5年ルール」(有期雇用が繰り返され5年を超える場合、従業員は無期雇用に転換することを請求できるという制度)ができたのもそうした安易さを避けるためです。
しかし、事例のようなケースでは、雇用している事業そのものが1年ごとに契約されるということですので、契約更新されなければ事業そのものがなくなってしまうわけです。もちろんその事業がなくなっても、他の事業に従業員を雇用し続けることができるならば、無期雇用としてもいいことは確かです。でも、中小企業の場合、そういう吸収力がないわけですから、有期雇用として雇うしかないでしょう。
【「契約終了」か「解雇」か】
現実の対応を考えても、「有期雇用」契約として雇用した場合、事例のケースにおいては「契約終了」ということになります。最初の契約の時、「●●社との契約が終了するまで」として有期雇用であることを明示しておけば、雇用終了も割とすんなりいくと思います。仮に「●●社との契約」が更新されたときは、雇用契約に「契約更新あり、●●社との契約が更新された時」としておけばよいのです。
一方、「無期雇用」として契約を結んだ場合、引き続き雇用しなければならず、それができなければ解雇としなければなりません。解雇となれば、当然、解雇予告制度に基づき、予告するか1か月分の給与を支払うことになるだけでなく、解雇無効を求めて争いになることも考えられます。そうなれば、解雇無効となる可能性も高く、トラブルは泥沼化することもありうることです。
【労働条件明示義務の内容】
2024年4月から、労働基準法が定める労働条件明示義務の内容が厳しくなりました。具体的には、有期雇用契約を更新する際の内容がかなり具体的になったことです。次のように具体的です。
①契約時及び契約更新の際に、就業場所・業務の変更の範囲・内容を明示
②契約更新上限の有無と内容
③無期転換申込機会の発生する契約更新時
これらの点を踏まえて、契約を締結・更新するようにしてください。
【この段階でどう対応できるか】
この段階で会社としてできることは、いくつかあります。一つは、他の会社も含めて新たな業務委託契約を締結できるところがないかどうかを模索することです。また、従業員を新たに雇用できる余地がないかどうかの検討です。従業員が再就職できる会社を紹介できるかどうかの検討も検討しておいたほうがいいでしょう。
ひとり一人の従業員については、面談する機会を作り、希望に応じて最大限雇用もしくは再就職先の紹介を行うことです。なるべく解雇による争いとならないよう最善を尽くすしかないと思います。