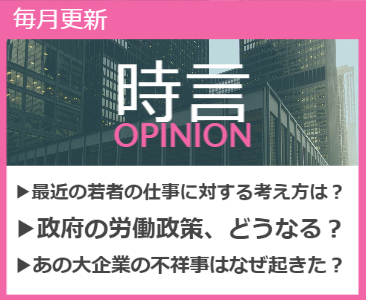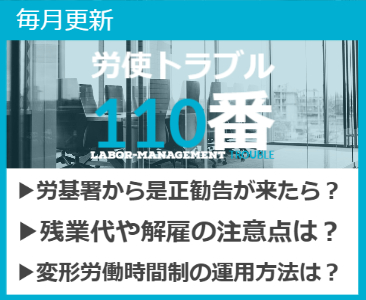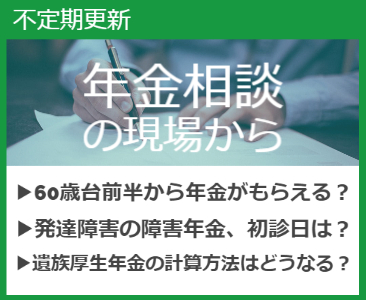労使トラブル110番
訪問介護(看護)事業部門でフレックスタイム制を採用できるか?
Q
医療法人です。法人内の訪問介護事業、訪問看護事業、ケアマネージャー部門の従業員から、利用者ごとの需要時間が大きく異なっており、フレックスタイム制を採用することはできないだろうかという要望が出されています。経営にとっても残業代抑制の一環としてそれに応えたいと考えていますがどうでしょうか。
A
【フレックスタイム制の要件と効果】
フレックスタイム制は、労働者が業務と生活の都合により、毎日の出退勤時間を按配できる制度として、主として専門的裁量労働の場合に会社と従業員の双方の利益に合致できるものであり、最近では育児や介護を行う従業員にとっても利用価値が高くなっています。2018年改正で、単位期間を1ヵ月以内から3ヵ月以内に拡張されました。
<要件>
①始業・終業時刻を各労働者の決定に委ねることを就業規則で定めること。
②労使協定の締結。協定で定める事項は、A労働者の範囲、B3ヵ月以内の単位期間(起算日を明らかにすること)、C働くべき総労働時間、D標準となる1日の労働時間の長さ、Eコアタイムを設定する場合にはその時間帯の開始・終了の時刻、Fフレキシブルタイムに制限を設ける場合にはその開始・終了の時刻。
③3ヵ月単位のフレックスタイム制の場合に特別に定める事項と労使協定の届出
<効果>
①遅刻についての心配がなく、労働時間の束縛感から精神的に解放される
②通勤ラッシュを避けることができる
③労働者ごとの生活リズム、体調に合わせて仕事ができる
④時間外労働の減少
⑤その他
【訪問介護(看護)事業の場合】
たしかに介護報酬の切り下げなどもあり訪問介護(看護)事業の経営はどこも厳しい状況に置かれています。もしフレックスタイム制を導入し、残業等の抑制につながればいいのですが、問題は「始業・終業時刻各労働者の決定に委ねる」という要件に合致しているかどうかだと思います。もし利用者ごとに担当者が決まっているような場合、利用者の需要時間に合わせて職員は動かなければなりませんので、労働者に労働時間を裁量する余地はなく、要件の第一を満たすことができません。しかし、職場の責任者が総量を把握し、その大枠の中で一人ひとりの労働者が自分の裁量の範囲で仕事をするというやり方が可能であれば、フレックスタイム制を導入することは不可能ではないでしょう。
何よりも、労働者側からフレックスタイム制の導入が要望されているわけですから可能となるよう体制をとれればいいと思います。
【就業規則と労使協定の規定例】
<就業規則の規定例>
第○条 従業員の過半数を代表する者との書面による協定によりフレックスタイム制を適用することとした訪問介護、訪問看護、ケアマネージャーの従業員の始・終業時刻については、第○条の始・終業時刻の規定を適用せず、当該従業員の自主的に決定するところによる。
2 ただし、始業につき労働者の自主的決定に委ねる時間帯(フレキシブルタイム)は、午前○時から午前○時まで、終業につき労働者の自主的決定に委ねる時間帯は、午後○時から午後○時までの間とする。
3 午前○時から午後○時までの間間(休憩時間を除く)については、必ず出勤のうえ(コアタイム)所定の勤務に従事しなければならない。
※労使協定でコアタイム、フレキシブルタイムを定めた場合は、2項、3項を就業規則に規定するようにします。
<労使協定の例>
第1条(対象労働者の範囲)
第2条(清算期間)
(例)毎月1日から月末まで
第3条(清算期間における総労働時間)
(例)1日当たり8時間に、清算期間における所定労働日数を乗じて得た時間とする。
第4条(標準となる1日の労働時間)
第5条(労働しなければならない時間帯(コアタイム))
第6条(選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム))
第7条(休憩)
第8条(労働時間の清算)
①所定労働時間を超過した労働時間に対しては、賃金規程の定めるところにより時間外労働手当を支給する。
②所定労働時間に不足が生じた場合には、当該時間については翌月分に繰り越して労働時間で清算することができる。ただし、翌月の月間法定労働時間の範囲内とする。翌月分で清算できないときは翌々月とし、以下同様に取り扱う。
……