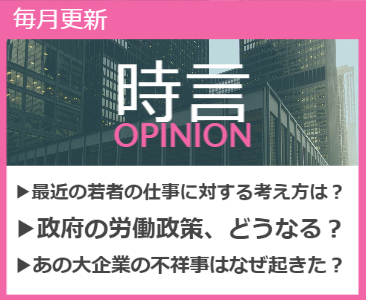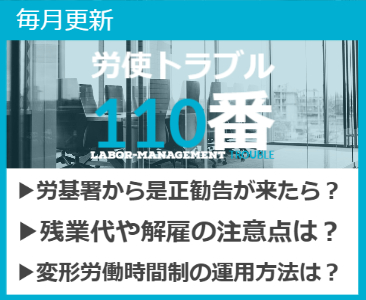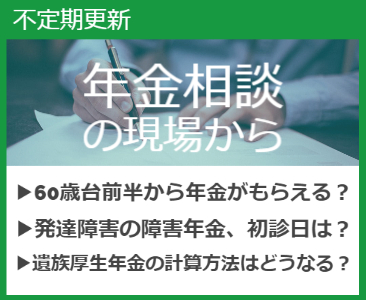労使トラブル110番
「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例」は非常勤職員も適用対象外か?
Q
人手不足ということもあり、65歳以降の高齢者を雇用したいと考えています。高齢者は人によって体力や病気のリスクなども違い、1年ごとに契約更新しながら状況を判断したいと考えています。最近、悪意ある者が、無期転換申込をした上で、「ずっと(死ぬまで)雇い続けてくれ」と言っており、対処に苦労しています。こうしたケースを防ぐためにはどうしたいいのでしょうか。
A
【定年後に継続雇用される高齢者が無期転換の対象外に】
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。これは同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換するというものです。その後、有期雇用特別措置法が平成27年4月1日に施行されました。この法律により、
①専門的知識等を有する有期雇用労働者と、
②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者について、
その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されることになりました。
【非正規職員が無菌転換後に定年となった場合の継続雇用も対象になる】
この特例では、正規職員が定年退職後に1年単位などで継続雇用となった場合に無期転換申込権の適用対象外となる場合が典型的ケースとされています。では、もともと有期雇用職員だった者が無期転換となり、その後定年退職となったケースはどうなるでしょうか?例えば、有期雇用で57歳まで契約更新を繰り返してきた非正規職員が、62歳に無期転換申込権を行使したときに、その後就業規則の適用により65歳で定年退職なり、65歳後にまた有期雇用者として継続雇用されるというケースです。
厚労省・都道府県労働局・労働基準監督署名のパンフレット(「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」)によれば、無期転換ルールの特例は、「定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者について」対象となるとしているのであり、元が正規労働者であったか、非正規労働者であったかは問われません。
【高年齢者雇用確保措置とは】
認定を受けるためには、最寄りの都道府県労働局に申請することになります。その際、高年齢者雇用確保措置として以下の「いずれか」を講じ、計画書を提出しなければなりません。
●高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
●職業能力の開発及び向上のための教育訓練等の実施
●作業施設・方法の改善
●健康管理、安全衛生の配慮
●職域の拡大
●知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
●賃金体系の見直し
●勤務時間制度の弾力化