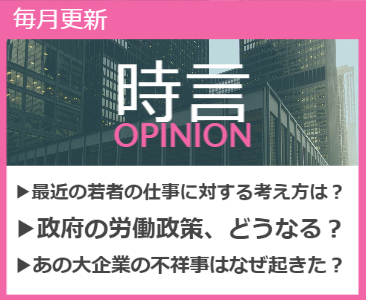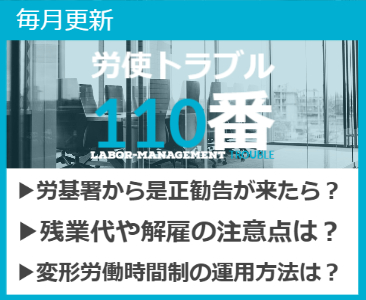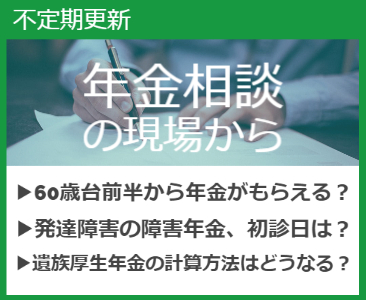労使トラブル110番
労働組合との団体交渉で不当労働行為となる場合とは?
Q
年末一時金をめぐって労働組合との交渉を行っている最中です。いまの経営状況から、昨年水準の一時金を支給することは難しく、かなり厳しい交渉となり、場合によっては決裂となるかもしれません。労組から「団交拒否だ!」と言われないためどこまで努力すればいいのでしょうか?
A
【労組法で不当労働行為とされる場合】
労働組合法第7条では、使用者による不当労働行為となる場合について規定しています。不当労働行為となる場合とは、
①使用者が個々の労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと又は労働組合の正当な行為をしたことを理由として、その労働者に対して不利益な取扱いをすること、及び労働組合に加入しないことあるいは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とするいわゆる黄犬契約を締結することを禁じる。
ただし、一定の条件のもとに、使用者が労働組合とユニオン・ショップ又はクローズド・ショップに関する労働協約を締結することを禁止するものではない。
②使用者が、正当な理由なく団体交渉をすることを拒むこと。
③使用者が、労働組合の結成・運営に対して支配、介入すること。
④使用者が、労働者が労働委員会に対して不当労働行為が行われた旨の申立てをし、若しくはこの申立てに対する地労委の処分につき中労委に再審査の申立てをし、又は労働委員会の不当労働行為の調査審問若しくは労働争議の調整の場合に証拠を提出したり、あるいは発言をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁止する。
【団体交渉の拒否とは】
前提として「正当な理由」なく拒むことを禁止するとしており、「正当な理由」として①団体交渉の対象となる事項が適切かどうか、②交渉担当者が適切かどうか、③交渉の日時・場所・人数等が社会通念上許容される範囲であるかどうかが問われます。これらが不適切な場合は正当な理由がある拒否ですから、不当労働行為とは言えません。
ではどのような場合に拒否したといい得るのか、具体的事情に応じて、裁判例なども紹介します。
<労使の誠意の問題>
「最終的にはなんらかの合意に達しえなかったとしても、その団体交渉の過程においては、双方は、自己の主張を相手方に十分納得さすべく誠意をもって交渉にあたらなければならない」(大阪地労委命令、大阪活版印刷事件、昭45.12.24)。使用者は誠意をもって交渉した以上、必ず協定に到達しなければならないという義務があるわけではありません。ここでいう誠意とは、譲歩できないならその根拠を示して反論する等の努力を指します。それを怠り、一方的に自己の主張を繰り返し、その結論を押し付けるようなことをしないということです。
「年末手当の支給、賃金増額の要求を交渉事項とする組合との団体交渉において、使用者が十分な経理的根拠を説明し、かつ、経理的に可能な相当限度まで譲歩した回答を提示したうえで、労働者側に対し、その要求の合理的事由を具体的に開示するよう求めた場合に、労働者がかたくなに自己の主張を譲るべからずものとし、右事由を開示することなく、再度団体交渉の申し入れに及んだような場合に、使用者が労働者側に妥結の誠意がないものとし、右申入れを拒否したからといってこれを不当と断ずることはできない」(順天堂大学団交拒否事件、東京高裁、昭43.10.30)とするものもあります。