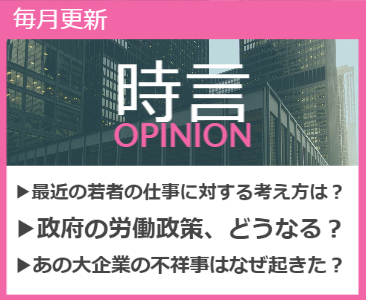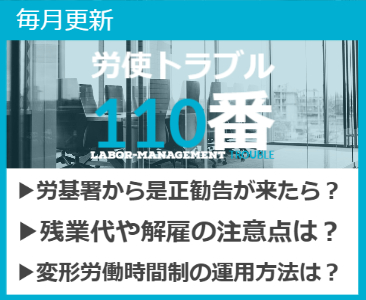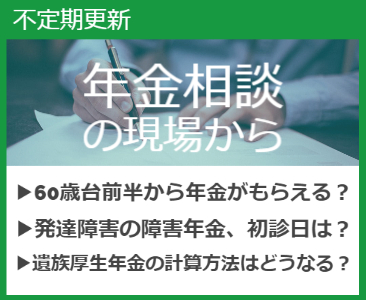年金相談の現場から
退職後の健康保険は、国保の被保険者か、任意継続被保険者か?
Q
会社をまもなく定年退職し、再雇用されるのですが、週30時間未満の勤務となり、健康保険の被保険者資格を喪失します。
定年後の健康保険制度は、国民健康保険の被保険者になるのが良いのか、任意継続被保険者になるのが良いのか、判断基準は何でしょうか?
A
【給付は国保も任意継続も変わらない】
国保と任意継続のいずれも医療費の自己負担割合は原則3割ですから、保険給付そのものに違いはありません。そうすると両者の違いは保険料負担の違いになります。
<国保料の決まり方>
国民健康保険は各市区町村の管轄になりますので、市区町村ごとに計算方法は違います。ですから、自分の国保料がいくらになるかは、各市区町村に聞いて教えてもらうしかありません。
ただし共通しているのは、前年度の所得と世帯人数及び年齢構成によって決まるということです。
一般に、退職した年度の国保料は、退職前の所得額によって算出されますから高くなると考えた方が良いでしょう。また、平均的には年間数十万円の国保料が想定されます。
【任意継続被保険者制度とは 】
任意継続被保険者制度とは、退職後2年間に限って、退職前の健康保険制度に加入し続けることができるという制度です。もし退職前が協会けんぽの被保険者であったなら2年間協会けんぽに加入でき、健康保険組合の被保険者であったなら引き続きその健保組合の被保険者になることができます。下記の条件がありますので注意して下さい。
①退職後2年間に限定されること
②保険料は全額自己負担(事業主負担はない)
③退職後20日以内に最寄りの健康保険制度の事務所に行き手続をすること
④保険料は毎月10日までに納付すること(1日でも納付が遅れると資格を喪失します)
【任意継続被保険者の保険料額の決まり方 】
任意継続被保険者の保険料は次のように決まります。
(退職時の標準報酬月額と加入する制度の全被保険者の平均の標準報酬月額のいずれか低い方)
×保険料率
上記の「いずれか低い方」というのは、例えば、退職時の標準報酬月額が30万円であったとするなら、協会けんぽの平成30年度の全被保険者の平均標準報酬月額が28万円ですから、低い方の28万円に保険料率を乗じることとなります。
逆に、退職時の標準報酬月額が22万円であった場合は低い方は22万円になりますから、22万円に保険料率を乗じます。
(なお健保組合の方の標準報酬月額の平均額は協会けんぽよりも高い傾向にあります)。
保険料率は都道府県によって違いますが、東京の協会けんぽの平成30年度の保険料率は、介護保険2号被保険者の場合は11.47%、2号被保険者でない方は9.90%です。
概していうと任意継続被保険者の方の保険料負担の方が、国保料の負担額よりも低くなるケースが大半です。もちろん最終的には市区町村で国保料を確認して決めるのが確実です。
また、2年間任意継続被保険者になった後に国保に加入すると、前年度の所得額がかなり低くなっているはずですから、退職直後に国保に加入するよりも負担はかなり軽くなるはずです。
※上記は、2018年10月時点の回答です。
【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。
【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。
【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。
【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。
【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム